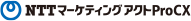コールセンター・コンタクトセンターの関連記事一覧です。
立ち上げから運用まで、コールセンター・コンタクトセンターに関する悩みをお持ちの方はぜひ参考にしてください。
-

コンタクトセンター
コールセンターにおけるオペレーター教育とは?重要性・育成ポイント・研修内容を徹底解説
-

コンタクトセンター
コールセンターの業務フロー・コールフローとは?ポイントを解説
-

コンタクトセンター
電話業務を効率化する方法は?課題・デメリット・改善策・おすすめツールを紹介
-

コンタクトセンター
コールセンターのKPIとは?重要指標や改善のポイントを解説
-

コンタクトセンター
ACD(着信呼自動分配装置)とは?仕組み・主な機能・導入メリット・注意点
-

コンタクトセンター
コールセンターのCSR・TSRとは?役割・業務内容・違いをわかりやすく解説
-
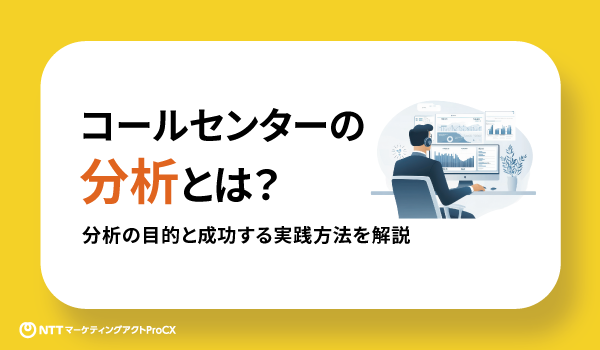
コンタクトセンター
コールセンターの分析とは?分析の目的と成功する実践方法を解説
-

コンタクトセンター
コールセンターの音声認識とは?機能や効果、導入のステップを解説
-
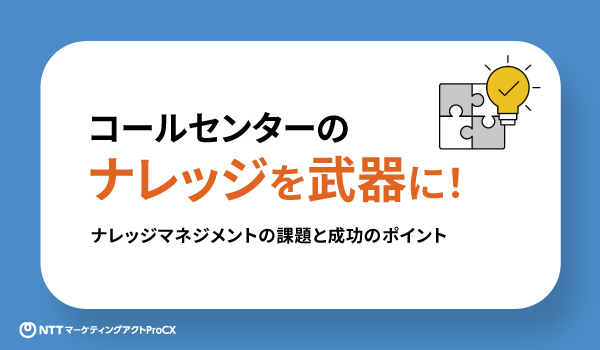
コンタクトセンター
コールセンターのナレッジを武器に!ナレッジマネジメントの課題と成功のポイント
-
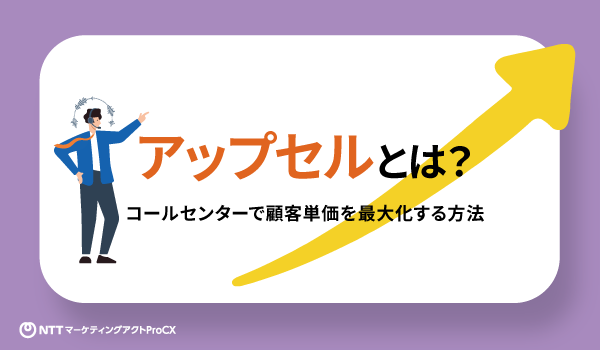
コンタクトセンター
アップセルとは?コールセンターで顧客単価を最大化する方法
-

コンタクトセンター
コールセンターのPBXとは?主な機能と選び方のポイントを解説!
-

コンタクトセンター
コールセンター効率化のポイントとは?よくある課題と改善策を解説